家族の安定と新たなチャレンジ
子どもたちはそれぞれ学校や保育園に馴染み、毎日元気に通っています。
妻はフルタイムのパートとして安定して働き、私も家族と穏やかな日々を過ごす中で、うつの症状はかなり改善してきました。
もちろん、クラウドソーシングの案件によっては一時的に調子を崩すこともあります。
しかし、長期にわたって落ち込むことはなく、比較的安定したメンタルで過ごせていました。
そんなある日、知人がIT系のコンサルティング会社を立ち上げたという話を耳にしました。
以前から少しでも仕事量を増やせればと考えていた私は、試しに連絡を取り、障害者雇用枠での在宅勤務ができないか相談しました。
結果、ハローワークとの調整を経て、ありがたいことに採用が決定。
在宅勤務という形で新たな仕事に取り組むことになりました。
出社勤務の始まりと生活の変化
当初は自宅での書類整理や軽作業が中心でした。
ところが、業務の中心が徐々にネットワーク関連に移行し、社内ネットワークにアクセスする必要が出てきました。
いつしか週1日の出勤が、週5日へ。
時短勤務ではありましたが、出社が前提となる働き方へと変わっていきました。
子どもたちは成長しており、長子も小学校6年生。
帰宅後も一人で過ごせるようになっていたため、私が夕食を作り、妻が帰宅する頃には家族揃っての時間を持てるようになっていました。
一見すると順調な日々。
しかし、ある問題が少しずつ浮かび上がってきました。
母の涙、そして見え始めた限界
出社するようになってから、母のもとを訪れる頻度が激減しました。
週末には顔を見せていたものの、買い物などもあり長時間話し相手になることは難しくなっていたのです。
最初は「無理しないでね」と私の体調を気遣ってくれていた母。
しかし、2ヶ月ほど経ったある日、私が夕食を作っていると突然泣きながらやってきました。
「全然顔を見せてくれない…。お母さんのことなんて、どうでもいいんでしょ」
必死に「毎週末は顔を出している」と説明しても、母は涙ながらに家へ戻っていきました。
妻と話し合った結果、長子に放課後の時間を使っておばあちゃんの家に顔を出してもらうことに。
幸い、母になついていることもあり、長子は快く了承してくれました。
それでもしばらくして長子がこう言いました。
「最近、おばあちゃん元気ないみたい。ぼーっとしてる時があるんだよね」
やはり、日常的な会話が減ったことが影響しているのかもしれません。
このままでは認知症の症状が進行してしまうのでは…という不安がよぎりました。
家族として、息子としての決断
まだ勤めて4ヶ月。しかも、知人が立ち上げた会社。
簡単に退職を申し出るのは、正直つらい判断でした。
けれど、妻はこう言いました。
「もしお母さんの認知症が進んだら、結局は私たちが全てを引き受けることになるよ。
あなたが無理して出勤するより、今のうちに戻った方がずっといいと思う」
確かにその通りです。
本来なら在宅勤務のはずが、気づけばフルタイムの外勤。
最低賃金に近い収入では、負担の方が大きいのかもしれません。
そして私は、再び在宅勤務に戻ることを決めました。
母のそばで、日々を共に過ごしながらできる範囲で働く。それが、今の自分にできる最善だと思ったのです。
再び、穏やかな時間へ
在宅勤務に戻ってからというもの、母の様子は明らかに改善しました。
私や子どもたちと日常的に会話を交わすことで、表情も明るくなり、認知症の症状もほとんど見られなくなりました。
もちろん、感情の起伏や突然の涙など、認知症特有の不安定さが完全になくなったわけではありません。
けれど、それでも母は「家族との時間」を通じて、安定を取り戻してくれたのです。
これは、決して特別なことではありません。
認知症は薬だけではなく、「環境」が進行度合いを大きく左右する病気です。
私たち家族のように、日々のコミュニケーションと寄り添いが、何よりの薬になるのかもしれません。
家族で支えるという選択
仕事と介護の両立は簡単ではありません。
それでも、「家族を支えるために自分がどうあるべきか」を考え抜いた末の決断でした。
私が母のそばにいることは、ただの「介護」ではなく、
「家族として当たり前の時間を共有する」という、シンプルであたたかな日々への回帰だったのです。
この経験が、同じような悩みを抱える方の参考になれば嬉しいです。
そして、介護に正解はなくても、誰かの心に寄り添う選択ができる社会であってほしいと願っています。
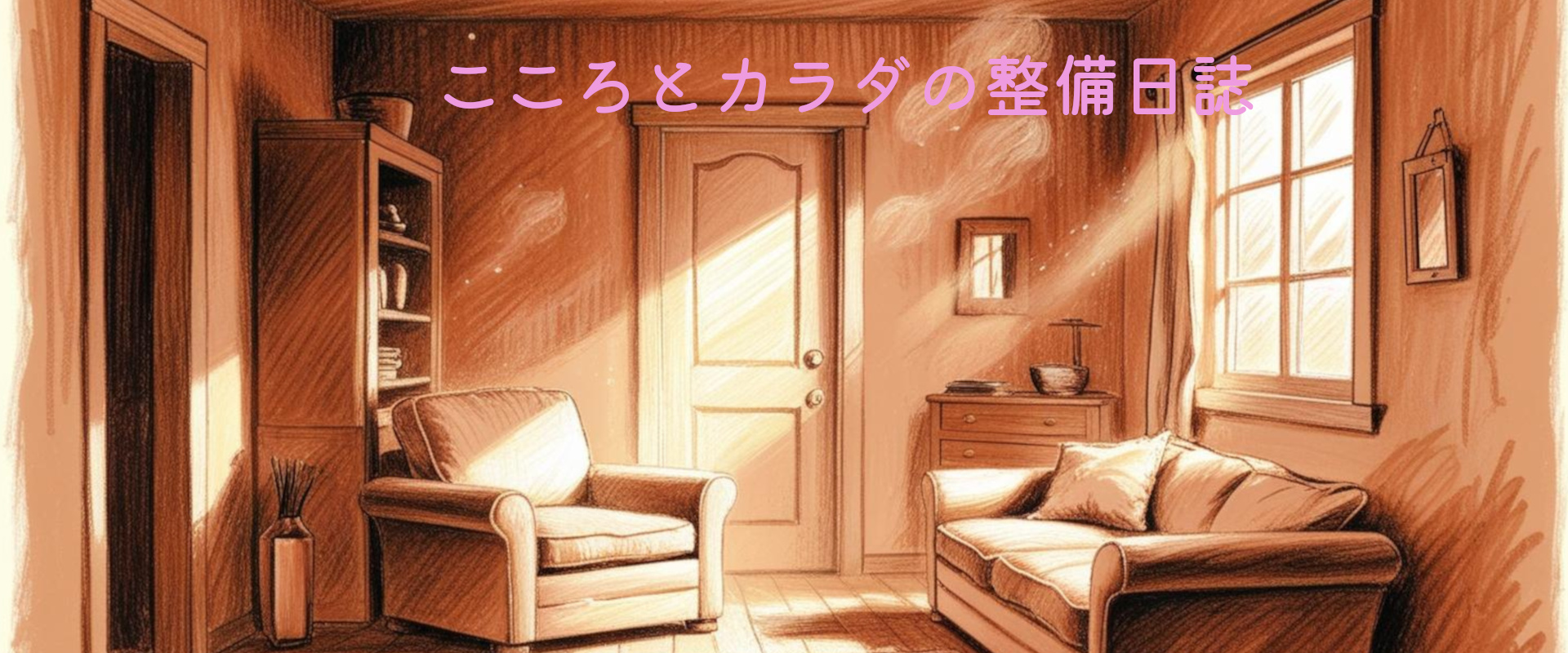

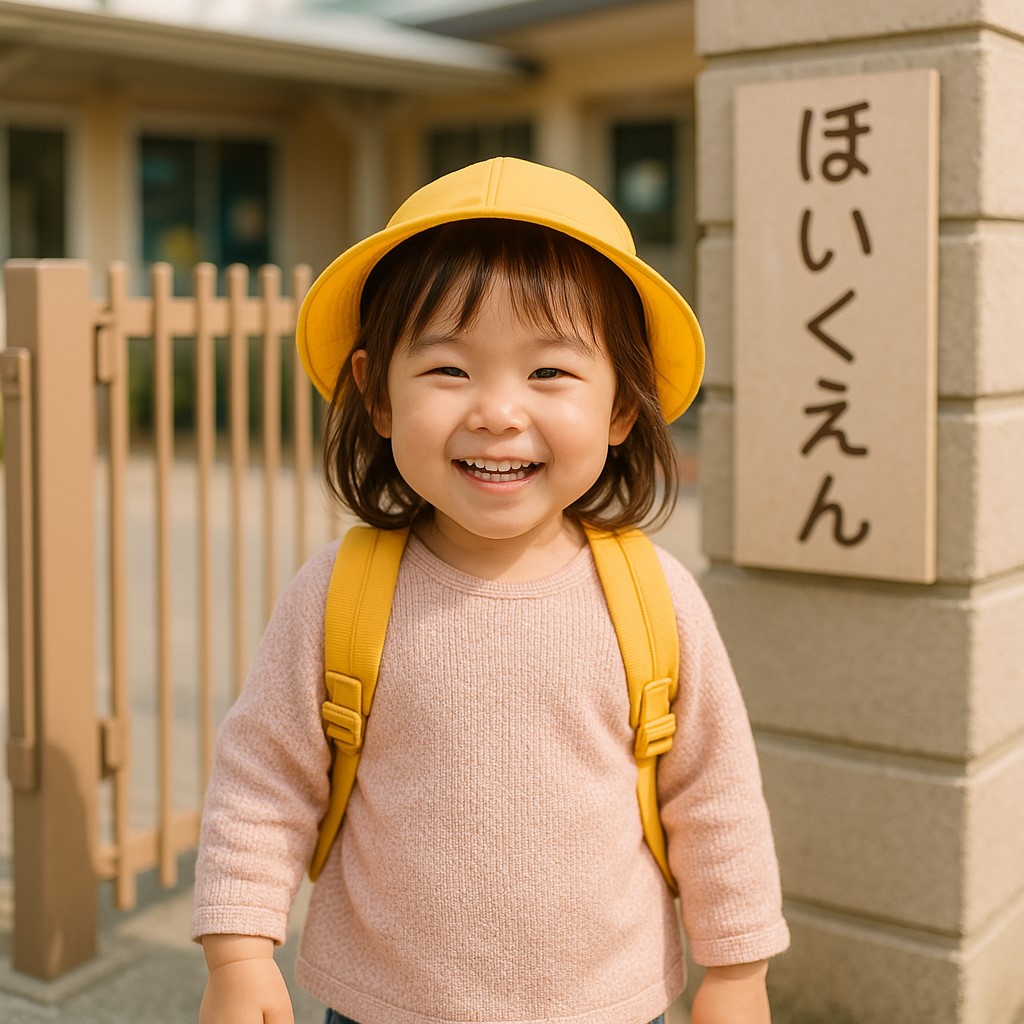

コメント