退院、そして新しい生活のスタート
次子の出産から1週間後、妻と赤ちゃんが無事に退院し、自宅に帰ってきました。
長子のときは10日ほど里帰りしていたのですが、今回は家族4人での生活をいち早く始めることにしました。
以前は平屋でしたが、今の家は2階建て。ベビーベッドを寝室に置くスペースがなかったため、1階で妻と次子が、2階の寝室で私と長子が寝ることになりました。
長子のときは母乳の出が悪く、夜中に起きて私がミルクを作る日々でした。
しかし今回は母乳の出がよく、ミルクの必要がほとんどなく、さらに紙おむつの性能も格段に上がっていたおかげで、夜中に泣くことも少なく、ほとんど手がかかりませんでした。
たまに夜泣きすることがあっても、おっぱいを飲めばすぐに泣き止み、そのまま妻と一緒に眠ってしまうことがほとんどだったそうです。
妻も「長子のときよりもずっと楽だよ」と笑って話してくれました。
私が担った家事と、変わっていく家族のかたち
出産後、妻は赤ちゃんのお世話で精いっぱい。自然と家事は私の担当になりました。
炊事、洗濯、掃除、ゴミ出し、布団干し……家の中のことはほとんどすべて、私が引き受けました。
それに加えてクラウドソーシングでの在宅仕事、そして認知症が少し進行してきた母の話し相手。
なかなか大変ではありましたが、充実した日々でもありました。
母は次子の誕生をとても喜んでくれましたが、長子のときと比べると実感が薄いようで、「かわいいね」と言いながらも、どこか反応が鈍いように感じました。
これも認知症の影響かもしれません。
長子も9歳になり、私や妻が少しの間出かける程度なら、次子の見守りをしてくれるようになりました。
さすがにおむつ交換までは難しいですが、それでも大きな助けになっています。
私は体調も比較的安定しており、うつがぶり返すこともなく、家族みんなで協力して日々を穏やかに過ごせていました。
次子の成長と、妻の新たな挑戦
次子が生後半年を迎えるころには、首もすわり、寝返りもできるようになりました。
私は母の家に行くときも次子を連れて行き、母もだんだんと慣れてきた様子です。
日中はミルク、夜は母乳と生活リズムも整ってきました。
長子のとき同様、ミルクの後のゲップ出しは私の得意分野で、今回も「けぷっ」と気持ちよく出してくれます。
私が抱っこするとすぐにゲップが出るのは、妻にも不思議がられるほどです。
そんなある日、妻が言いました。
「そろそろ、外に仕事に出ようかな? あなたが家事をやってくれてるし、ずっと家にいてもやることがないし」
「無理に働かなくてもいいよ。私が仕事の量を増やせば、なんとかやっていけると思うよ」と返したのですが、妻の気持ちは固いようでした。
当初は、以前働いていたファミレスに戻ろうと考えていたようですが、昔の同僚から「最近はシフトも減っていて、なかなか働けない」と聞き、別の職場を探すことになりました。
ハローワークに通いながら、条件に合う求人を探す日々。
気になる求人票はすべて印刷し、家に帰ってから私と一緒に検討しました。
その中に、ある一件の求人が目に留まりました。
パート勤務ながらフルタイムで、ボーナス・有給ありという好条件。
ダメ元で応募してみたところ、面接と筆記試験を経て、見事採用されました。
妻は「赤ちゃんを預けてまで外で働くのは不安」と話していましたが、
「あなたなら大丈夫。家のことは任せて」と私が伝えると、前向きな気持ちで新たな一歩を踏み出しました。
変化の中でも、家族で支え合いながら
次子の誕生をきっかけに、我が家にはさまざまな変化が訪れました。
家事や育児、仕事、母の介護など、やることは山ほどあります。
でも、家族で協力しながら、少しずつ前へ進むことができています。
「自分が今できることを、できる範囲でやる」
うつを経験した私だからこそ、このバランス感覚が大切だと感じています。
これからも、無理をせずに。
家族みんなで寄り添いながら、歩んでいきたいと思います。
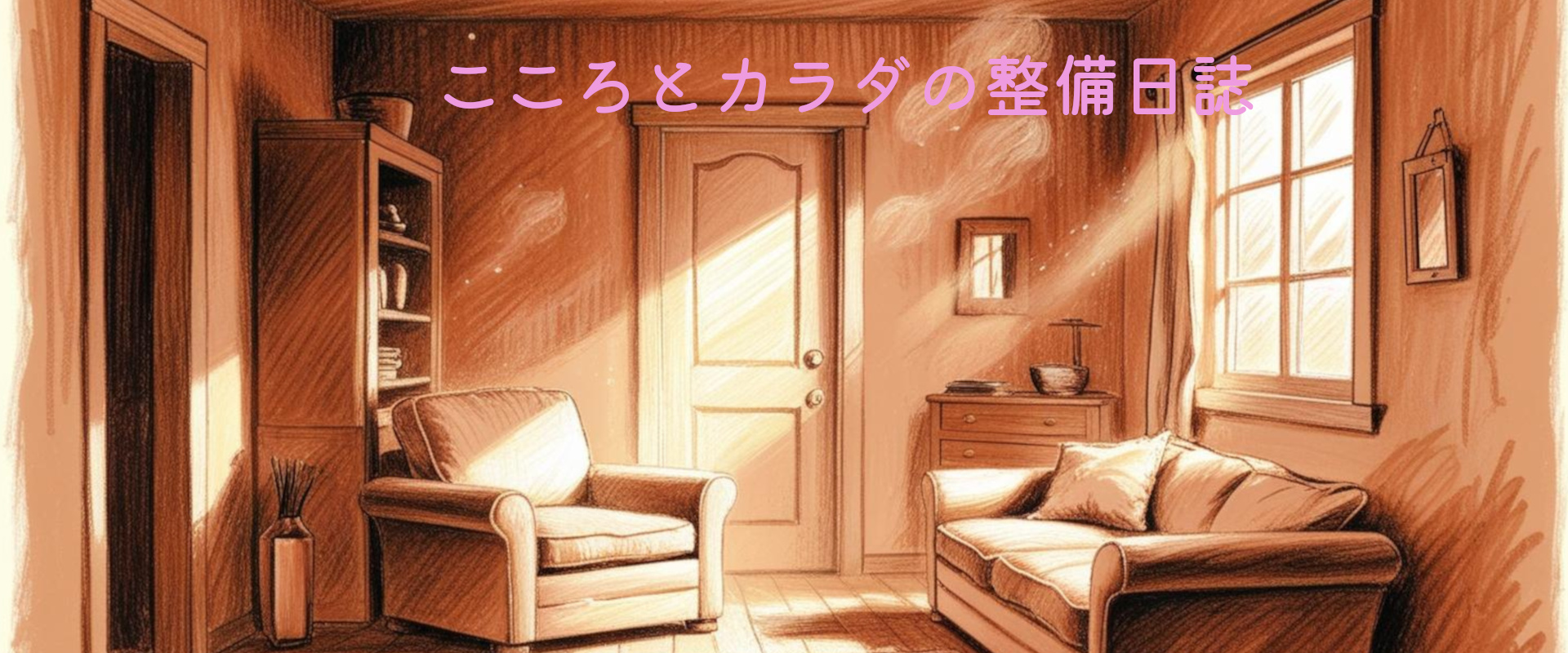



コメント