父のいない家に残る寂しさと母の変化
四十九日の法要が終わると、母もようやく一息ついたようでした。しかし、それと同時に、父のいない家に寂しさを強く感じるようになったようです。夜になると頻繁に電話をかけてくるようになり、何気ない会話を求めることが増えました。
両親の住んでいた家は築二十数年の6LDKと広く、夫婦2人で住むには十分な広さがありました。しかし、父が亡くなったことで家は今まで以上に広く感じられ、母は一人でいることの孤独をより強く感じていたようです。
母との同居を考える
母のそんな様子を見て、私は妻と相談し、同居することを提案しました。妻は母と仲が良く、快く了承してくれました。そして、さっそく母に同居の話を伝えました。
母は喜んでくれたものの、同居に対する不安も抱えているようでした。長年一人で家を切り盛りしてきたため、突然家族が増えることに戸惑いがあったのかもしれません。
そこで、母がこれまで住んでいた母屋から、すぐ隣にある「離れ」に移ることを提案しました。離れは1LDKで十分な広さがあり、何かあったときにはすぐに様子を見に行ける距離です。この案に母も納得し、私たち家族が母屋に住むことになりました。
引っ越し作業の大変さ
引っ越しを始めるにあたり、まずは母の荷物の整理から行いました。長年住んでいた家だけあって、不要な家具や物が多く、それらを仕分けるだけでも相当な時間がかかりました。
引越し業者を頼むことも考えましたが、時間をかけて荷物を整理しながら進める必要があったため、結局私と妻の二人で行うことにしました。母屋から必要なものを離れに移し、不要なものは処分する。この作業だけで数週間を要しました。
その後、私たち家族の引っ越しを進めました。こちらは荷物が比較的少なかったためスムーズに進みましたが、引っ越し2件分を自力でこなすのはかなりの労力でした。
精神的な安定と医師の指摘
父が亡くなってからこの頃まで、私のうつの症状は比較的軽い状態を保っていました。不安や疲労はあったものの、以前のような強い精神的な落ち込みは感じませんでした。
定期的に通っていた精神科のクリニックで、主治医にそのことを報告すると、「今は気が張っているんだろうね。気をつけないと、この後、反動で調子を崩すかもしれない。少しでも具合が悪くなったら、すぐに診察を受けに来るように」と注意を受けました。
いわゆる「軽躁状態」になっている可能性があるとのことでした。普段から躁うつの波をなだらかにするためにラミクタールを服用していたため、大きな躁状態にはならなかったようですが、それでも注意が必要な時期でした。
子どもの成長と新たな喜び
ちょうどこの頃、子どもが小学校1年生になりました。私がうつに苦しんでいたため、保育園時代の行事にはほとんど参加できませんでした。しかし、このときの私は比較的落ち着いており、保育園の卒園式と小学校の入学式には参加することができました。
これまでの自分を振り返ると、子どもに対して十分な父親でいられなかったという後悔がありました。しかし、このときは心から「子どもの成長が嬉しい」と思えました。
また、子どもには保育園に入ったころからカシオのポータブルキーボードを買い与えていました。この頃には簡単な楽譜なら読んで演奏できるほどに上達していました。そこで、小学校に入学すると同時にヤマハの音楽教室に通うことになりました。(そのために、妻が少しパートの量を増やしてくれました。)
子どもは集団でのレッスンにあまり馴染めないようでしたが、それでもどんどん上達していきました。3年間続けた結果、最終的には教室内で誰よりも上手になり、クリスマス会では相当難しい曲を演奏して周囲を驚かせました。
その演奏を聞いた先生が、「このままグループレッスンを続けるよりも、個人レッスンに移ったほうがいい」と勧めてくれました。結局、小学校を卒業するまで個人レッスンを続けることになり、最後のレッスンの際には先生が「時間がなくなってしまうのが寂しい」と言ってくれたそうです。
家族との暮らしと精神の安定
父の死をきっかけに、母と同居することになり、環境が大きく変わりました。引っ越しは大変でしたが、それによって母の寂しさを和らげることができたのは良かったと思います。
また、子どもの成長を身近で感じられたことは、私にとって大きな喜びとなりました。これまでうつの影響で、家族と十分に関われなかったことへの後悔はありますが、このときは「これからできることを大切にしよう」と前向きに考えることができました。
医師の指摘通り、気が張っていたことで調子が良かったのかもしれません。しかし、この安定した時期を活かして、少しずつ前へ進もうとする気持ちが芽生えていたのも事実でした。
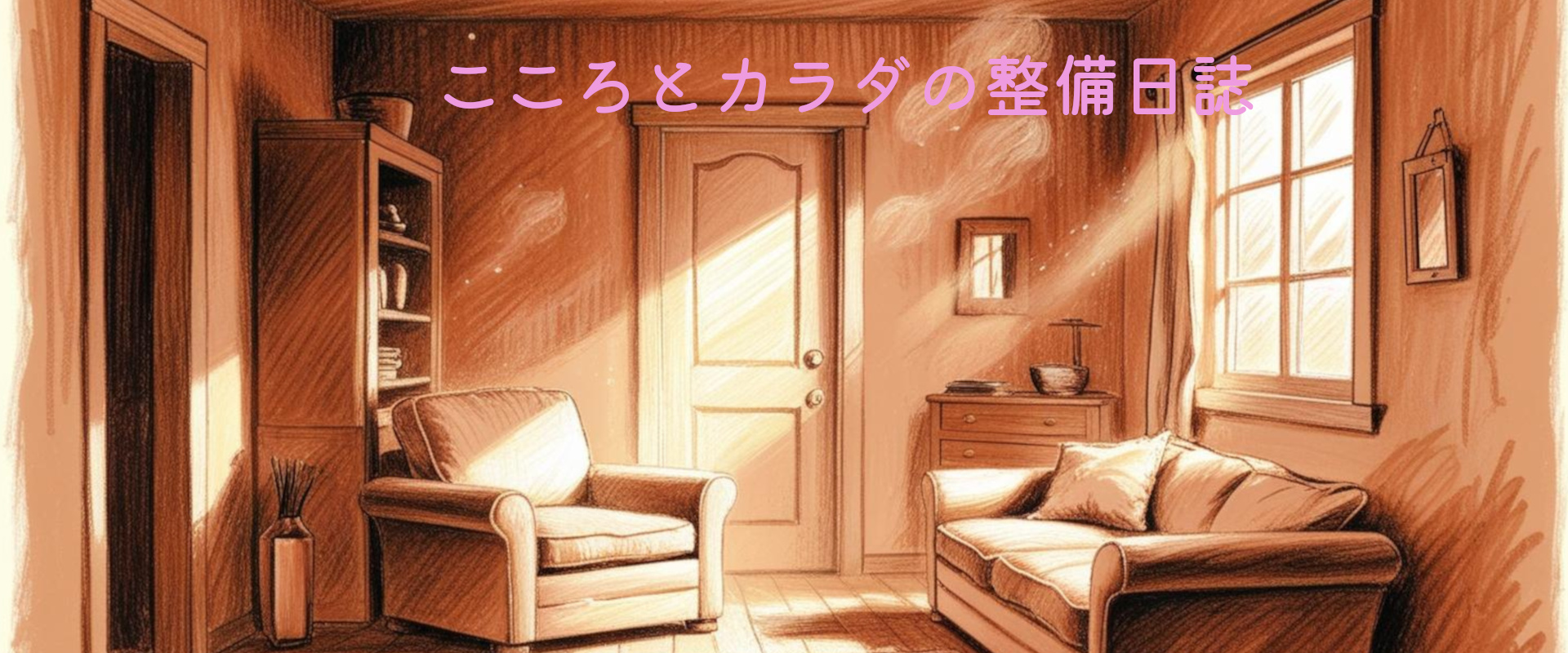



コメント