父の最期の別れと葬儀の準備
父が亡くなり、病院から自宅へと連れ帰ることになりました。病院に待機している葬儀社が自宅まで搬送してくれるとのことで、そのままお願いすることになりました。本来であれば、事前に決めていた葬儀社へ連絡するのが良いのかもしれません。しかし、突然のことで冷静に判断する余裕はなく、流れに任せる形となりました。
幸いにも、私たち家族は万が一のために各自が互助会の会員になっていました。そして、偶然にもこの葬儀社がその互助会と提携していたため、そのままスムーズに葬儀の打ち合わせへと移ることができました。
まず、父を寝かせる布団の準備が必要でしたが、これは最期の入院直前に使用していたものをそのまま使うことにしました。次に、葬儀の詳細を決めていきました。式場、祭壇の種類、骨壺や棺桶のデザイン、香典返し、枕花の種類など、ひとつひとつ決定していきます。また、菩提寺に連絡し、お布施の相場を確認してもらいました。
打ち合わせは2時間もかからずに終了し、ひとまず皆が休息を取ることになりました。しかし、父が一人で寝るのは寂しいのではないかということで、私と子ども、そして母が一緒に過ごすことになりました。
翌日、枕花が届きましたが、大きなユリの花がポトリと落ちてしまい、交換してもらうというハプニングもありました。時間が経つにつれ、出棺の時刻が近づいてきました。
湯灌の儀式では、父が生前、旅行に行く際によく着ていた服を着せてもらいました。しかし、それを見た母は、「お父さん、まだ元気だったときみたい。こんな服にするんじゃなかった」と泣き崩れてしまいました。その姿に、改めて父の存在が失われたことを実感しました。
出棺の際には、ご近所の方々に手伝っていただき、霊柩車へと乗せました。葬儀は近所のセレモニーホールで執り行うことになり、そのまま通夜へと移りました。私たちは、あまり大々的な葬儀にはしたくないと考えていました。しかし、ご近所の方々から周囲に話が伝わったのか、思っていたよりも多くの人々が最後のお別れに訪れてくださいました。
その夜は家族全員でセレモニーホールに泊まりました。
葬儀と火葬、父との最後の別れ
翌朝、火葬場へ向かいました。
母は、火葬の瞬間を見届けながら、静かに涙を流していました。私や妻、子どもも涙を堪えることができず、父に最期の別れを告げました。
火葬が終わり、葬儀が執り行われました。前夜の通夜にも増して、多くの方々が参列してくださいました。母は、このときには落ち着きを取り戻していたように見えました。しかし、内心では強く悲しみを抱えていたことは、表情からも伝わってきました。
葬儀が終わると、位牌と骨壺を持ち、家へ帰りました。その後、菩提寺にお布施を届け、一連の儀式が完了しました。
葬儀に関する一連の手続きを進める中で、葬儀社との打ち合わせ、菩提寺の住職の送迎、火葬場で待機する間の食事やお酒の準備、初七日の準備など、ほとんどの手続きを私と妻が進めました。
実は、私と父の関係は決して良好ではありませんでした。
父は私の病気(うつ病)について理解を示してくれず、むしろ厳しく当たることが多かったのです。さらに、私が結婚した当初から、妻と家事を分担していることも苦々しく思っていたようでした。昔気質の人間であり、「家事は女性がやるものだ」という価値観を強く持っていたのです。
それでも、私はもちろんのこと、妻も実に献身的に対応してくれました。そんな妻の優しさを改めて実感した出来事でした。
葬儀後の手続きと終わらない事務処理
一連の葬儀が終わり、ようやく一区切りつきました。
しかし、ここからが本当に大変な作業の始まりでした。
- 生命保険金の請求
- 水道・電気・ガスなど公共料金の名義変更
- 父が自営業だったため、税務署への廃業届の提出
- 世帯主の変更届提出
- 健康保険および年金の資格喪失手続き
- 遺族年金の請求手続き
- 銀行口座の凍結解除(遺産分割協議書の作成が必要)
遺産分割協議書の作成にあたり、父の戸籍謄本を出生時から現在までさかのぼって揃える必要がありました。これは思っていた以上に手間のかかる作業でした。
通常であれば、遺産分割協議書の作成は司法書士に依頼するのが一般的です。しかし、費用を節約するために、私自身が手続きを進めることにしました。
手続きを進めていくうちに、「いつになったら終わるのだろう?」という不安が募っていきました。やるべきことが次々と増え、いくら進めても終わりが見えません。
さらに、四十九日の法要の準備も進めなければなりませんでした。
- 参列者の選定
- お布施の額の確認
- 石材店への納骨依頼
やるべきことは次々と増えていきました。
そして、ようやく四十九日の法要が終わり、本当に一段落ついたのです。
父の死を通して学んだことと、これからの人生
葬儀や各種手続きを通じて、私は家族の大切さや人生の終わりに向き合うことの重さを痛感しました。
父との関係は決して良好とは言えなかったかもしれません。
しかし、最期の別れを迎えたとき、私は父を心から見送ることができたと感じています。
また、この経験を通して、事前の準備の重要性も実感しました。
葬儀や手続きに関しては、何も知らない状態で進めると、予想以上の負担がかかります。
もしものときに備え、必要な情報を整理し、事前に家族と話し合っておくことの大切さを痛感しました。
父が残したもの、そして父の死を通して得た教訓を胸に、これからの人生を歩んでいこうと思います。
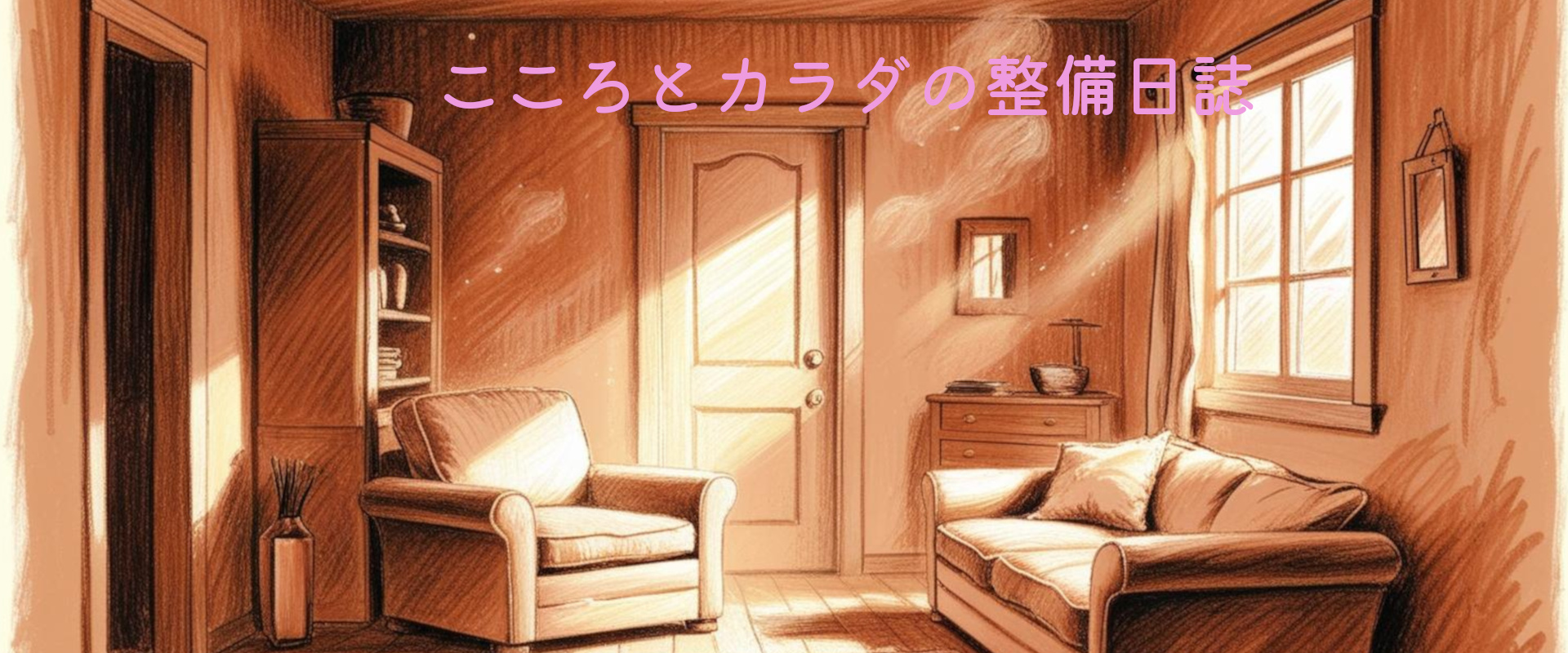

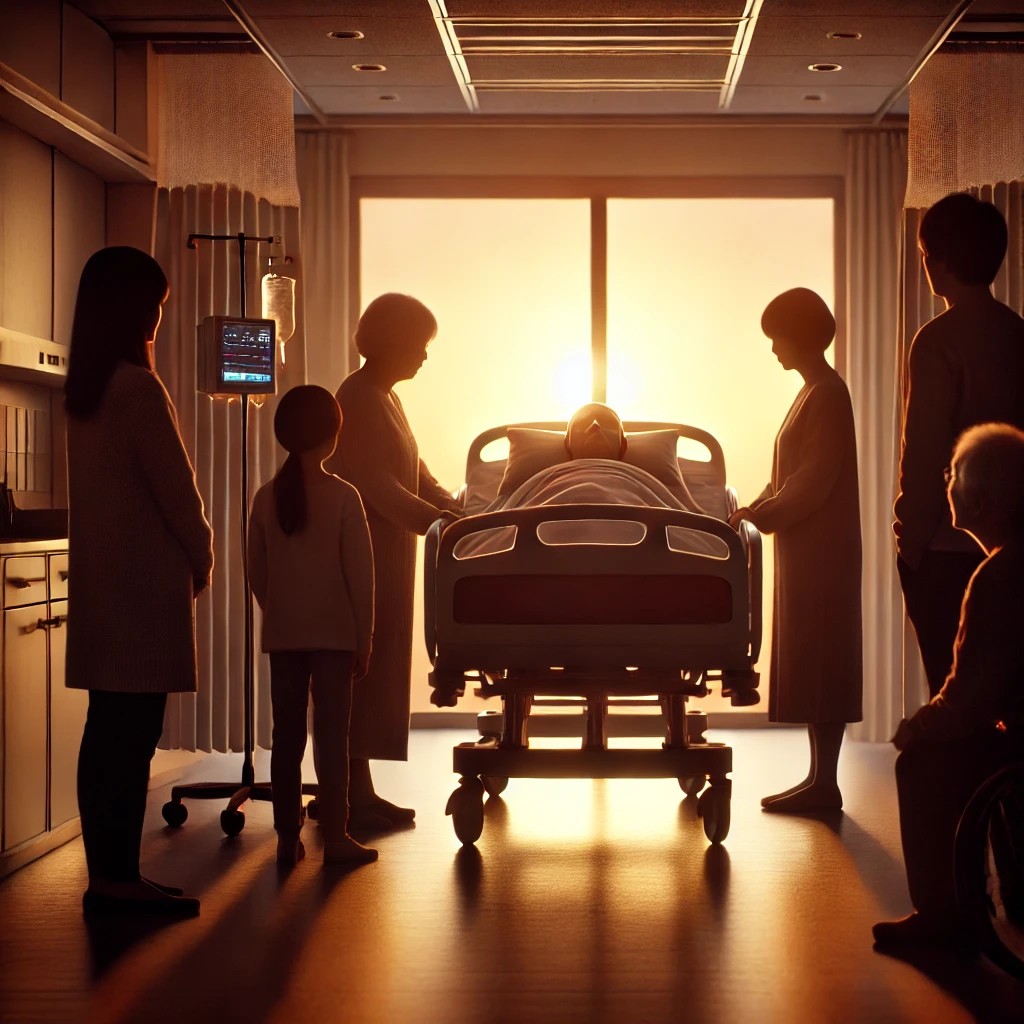

コメント